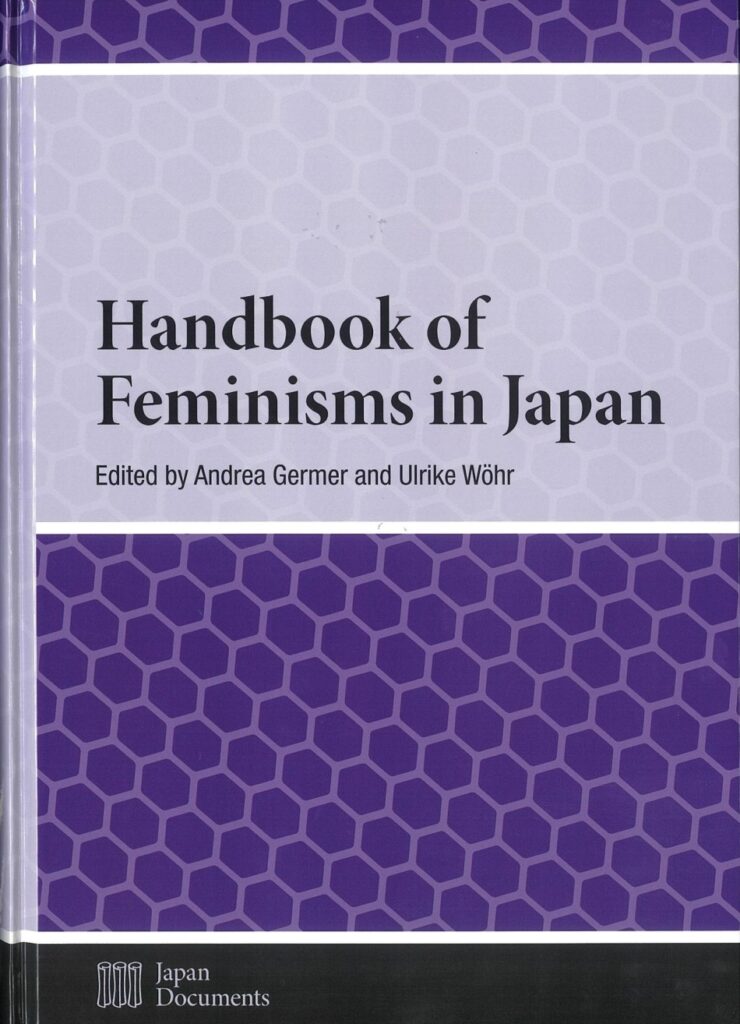
2021年8月10日に亡くなった、山川菊栄記念会代表だった井上輝子さんが賀谷恵美子さんとともに書いた論文を含む、ゲルマー、ヴェーア編 Handbook of Feminisms in Japan(Japan Documents, JA) 『 日本におけるフェミニズム・ハンドブック』、極東書店、2025年)がすでに刊行されています。
アンドレア・ゲルマー氏(ハインリヒ・ハイネ大学デュッセルドルフ校)とウルリケ・ヴェーア氏(広島市立大学)の二人が編者となって、46人の国内外の気鋭のジェンダー研究者を集め、現代日本のフェミニズムの動向を多角的に俯瞰してみせているもので、特に海外の日本研究者を読者対象としています。テーマはラディカルなフェミニズム、母性主義、アナーキズム、文学、宗教、ポルノグラフィといった広範なトピックを余すところなくすくいあげようとしており、ハンドブックといってもずっしりとした重厚さをもっています。
井上輝子さんと賀谷恵美子さんの共著論文は、この冒頭の第1章に置かれ、Academia: Gender Studies, Women’s Studies and Feminist Movements ( 「アカデミア:ジェンダースタディ、女性学とフェミニズム運動」)として掲載されています。山川菊栄がつくった婦人問題懇話会の会報で、1974年に二人は合衆国のWomen’s Studyの動向を「女性学」として紹介しました(賀谷恵美子、辺(ほとり)輝子共著「アメリカの諸大学の女性学講座」『婦人問題懇話会会報』20号)。それから半世紀近い歳月のジェンダー研究と女性学、そして市民運動の関係性を論述した内容となっています。
山川菊栄については、エリッサ・フェイソンさんの書いた第31章「Socialism and Marxism: Feminist Critique of Women’s Labor under Capitalism( 社会主義とマルキシズム:資本主義下女性労働のフェミニスト評論)」のなかで、戦前からの評論活動と赤爛会結成、そして戦後の労働省婦人少年局長就任に触られています。
フェイソンさんと記念会は交流があり、2012年7月に来日されたとき、まだ江の島にあった神奈川県立女性総合センターと山川菊栄文庫の見学に、井上輝子さん、岡部雅子さん、佐藤礼次さんの三人が同行したりしたことがありました。井上さんは鬼籍に入りましたが、こうして同じ書籍に名前が並んだことをきっと喜んでいることでしょう。
なお、編者のゲルマー氏とヴェーア氏にヴェラ・マッキー氏が加わった、Gender, Nation and State in Modern Japan(「ジェンダー、近代日本の国民国家と国家」)がルートリッジから2014年に刊行され、英語圏の基本書として流通しています。
*A.ゲルマー、U.ヴェール編 「日本におけるフェミニズム・ハンドブック
Handbook of Feminisms in Japan」(28,875円・税込)の購入については、極東書店サイトへお申し込みを。
*井上輝子さんについては、「日本婦人問題懇話会の軌跡サイト」に追悼ページがあります。